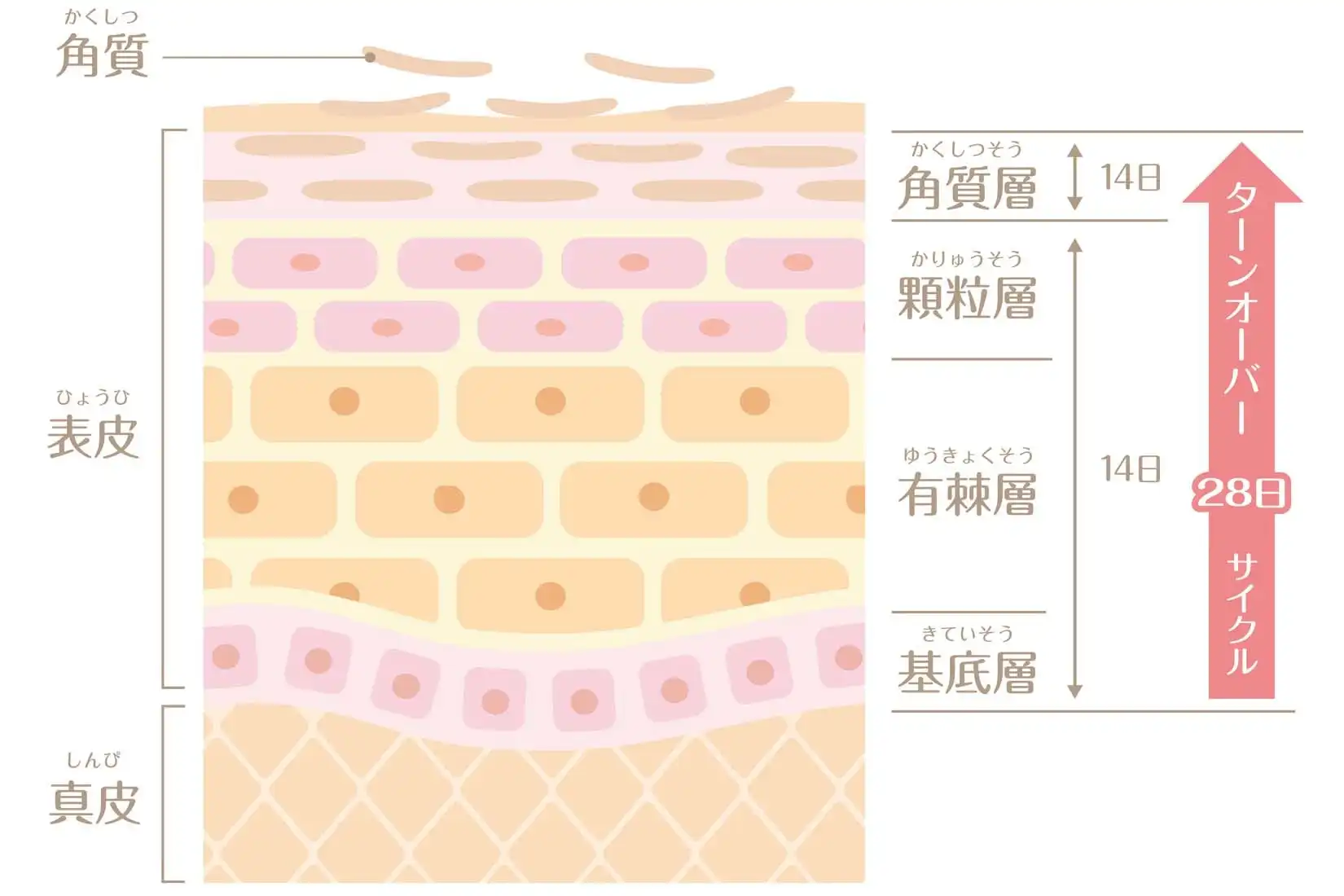冷え取り靴下ってどんなもの?選び方のポイントを解説

「冷え取り靴下って効果ある?」「どの靴下を選べばいいの?」
足が冷えやすくて、悩んでいる人は少なくありません。冷え取り専用の靴下があると耳にして、普通の靴下と何が違うのか気になる人もいるでしょう。
そこで今回の記事では、冷え取り靴下とは何かと、特徴や種類について詳しく解説していきます。また、冷え取り靴下の選び方も紹介していきますので、ぜひ参考にしてください。
冷え取り靴下とは?

冷え取り靴下とは、足元を温めて血行を促すのに役立つ靴下のことをいいます。冷え取り靴下は、秋冬の足先の冷えに悩む人や、夏でも冷房で足が冷たいと感じる人に向けて作られています。
指の形状や素材は製品によって異なるため、一概に「こういうものが冷え取り靴下だ」とは言えません。一般的な靴下とは違い、下半身の冷え対策を目的として素材や形にこだわって作られた靴下が、冷え取り靴下だと言えるでしょう。
冷え取り靴下の種類は?

冷え取り靴下には、形と素材、用途によっていくつかの種類があります。代表的なタイプは、以下の4種類です。
- インナータイプ
- 1枚で履けるタイプ
- 重ね履き用のセットタイプ
- つま先だけを覆うハーフタイプ
それぞれについて、詳しく解説していきます。
インナータイプ
冷え取り靴下には、重ね履きのインナーとして使用するタイプの靴下があります。形状は五本指ソックスで、シルクなど蒸れにくい素材が使われています。
足指の間にかいた汗が冷えると、足が冷えたと感じる人も少なくありません。冷房冷えとともに、「汗冷え」の予防にも、吸湿性放湿性の高いシルクはおすすめの素材です。
1枚で履けるタイプ
冷え取り靴下には、1枚で履けるタイプもあります。1枚で履ける冷え取り靴下には、二重構造になっていて重ね履きと同じような効果が得られるものや、裏起毛素材の靴下などがあります。
重ね履きは靴下の洗濯物が増えるのが嫌だという人や、忙しくて靴下を何枚も重ねて履くのが面倒だと思う人に選ばれやすいタイプです。
重ね履き用のセットタイプ
冷え取り靴下には、重ね履き用に2足セットや4足セットで販売されているタイプもあります。セット販売されている冷え取り靴下は、重ね履きすることを前提として作られているため、中の靴下は薄手で蒸れにくい素材のもの、外側の靴下は口ゴムがきつくならない仕様になっているなど、快適に履けるような工夫がみられます。
重ね履きをしてみたいけれど、靴下選びに迷ってしまう人には、セット販売されている冷え取り靴下を試されると良いでしょう。
つま先だけを覆うハーフタイプ
冷え取り靴下には、つま先だけを覆うハーフタイプのものもあります。主に夏の冷房対策や、オフィスでの着用にもおすすめです。
ハーフタイプであれば、ストッキングやタイツの下に履いても目立ちにくく、パンプスの下にも着用できます。窮屈感が少なく気軽に履けるのが魅力です。
冷え取り靴下の選び方

ここまで紹介してきた通り、冷え取り靴下には種類がたくさんあって選ぶのに迷うという人もいるでしょう。冷え取り靴下を選ぶときは、以下の5つに着目してみてください。
- 履くシーンで選ぶ
- 素材で選ぶ
- 指先の形で選ぶ
- 丈の長さで選ぶ
それぞれのポイントを詳しくみていきましょう。
履くシーンで選ぶ
冷え取り靴下は、履くシーンにあわせて選びましょう。日中、屋外で活動するときは、重ね履きタイプではなく1枚で履けるタイプがおすすめです。
重ね履きタイプは、靴下が途中でずれたり、分厚くて靴を履くと違和感があったりするのが嫌だという人も少なくありません。
一方で、自宅でリラックスするときに履く冷え取り靴下を選びたい人は、重ね履きタイプでもよいでしょう。また、足が窮屈に感じるのが嫌な人は、口ゴムがゆるい靴下を選ぶのもひとつです。
素材で選ぶ
冷え取り靴下は、素材で選ぶのもおすすめです。化学繊維の靴下は、保温性が高いため足冷え対策に向くと思われがちですが、通気性はよくありません。汗をかいても吸収されにくいため、逆に汗冷えを起こしてしまう恐れがあります。
また、化学繊維は帯電性があり静電気が起きやすいというデメリットも見逃せません。静電気が起こりやすいと、ストレスを感じるという人もいるでしょう。
合成繊維よりも、汗を吸収して蒸れにくく、静電気の起こりにくい天然素材のウールやシルクをおすすめします。
指先の形で選ぶ
冷え取り靴下は、デザインで選ぶのもよいでしょう。冷え取り靴下の中には五本指靴下が多くみられます。五本指靴下は、足の指が1本ずつ袋に包まれていることで、足の指にかいた汗が吸収されやすいためです。また、足の指が動かしやすいことで血行促進の効果も期待できます。
しかし、五本指靴下の見た目が気になるという人も少なくありません。五本指靴下の中には、一見すると五本指靴下にみえないけれど中で足指の間に仕切りがあるタイプがあります。五本指靴下に抵抗がある人は、そんな五本指靴下を選んでみるのもよいでしょう。
丈の長さで選ぶ
冷え取り靴下は、丈の長さで選ぶのも一つの方法です。足首よりも長いクルー丈や、膝下まであるタイプが一般的ですが、前述の通りハーフタイプもあります。
しもやけや冷え性に悩む方や体の冷えやすい妊婦の方は、足首を覆うクルー丈がおすすめです。内くるぶしの上には、三陰交(さんいんこう)という、冷え性や生理不順などに効くツボがあります。三陰交は、内くるぶしの最も高い部分から指4本分上の位置にあります。三陰交が隠れる程度の長さを選ぶとよいでしょう。

三陰交は、内くるぶしの一番高いところから3寸(指4本分)です。
また、ふくらはぎには血液循環を担う筋肉があるため、ふくらはぎをしっかりと温められる長めの靴下を選ぶのもよいでしょう。
冷え取り靴下についてよくある質問
冷え取り靴下を購入する前に、冷え取り靴下をやめた人もいる、寝るときは履かないほうがいいなどの情報を耳にして、不安に思うこともあるでしょう。ここでは、冷え取り靴下に関する疑問にお答えしていきます。
やめた人もいるって本当?
冷え取り靴下をインターネットで調べると「やめた」「必要ない」などと出てきて、真相が気になります。「冷え取り靴下は必要ない」という声の多くは、重ね履きタイプについての意見が多く見られます。
「靴下を重ね履きすると靴のサイズが変わってしまうのが嫌だ」、「忙しい朝に何枚も靴下を重ね履きするのが面倒だ」という人も少なくありません。また、洗濯物が増えてしまうのも、重ね履きのデメリットと言えるでしょう。
冷え取り靴下の重ね履きが嫌な人は、1枚で履けるタイプを選んでみるのもおすすめです。
寝るときは履かないほうがいい?

冷え取り靴下は、寝るときには履かないほうがよいのか気になる人もいるでしょう。冷え取り靴下にかかわらず、足の寒さが我慢できず、寝るときに靴下を履いている人もいると思います。ですが実は、寝るときに靴下を履くと、かえって体が冷えたり、睡眠の質が低下したりすることがあります。
人が眠りにつくには、深部体温が下がり、外の気温との差が生じて眠気がやってくるというメカニズムがあります。深部体温が下がるには、皮膚の表面から体内の熱を外に放出する必要があります。そこで足を靴下で覆ってしまうと、熱がこもり深部体温が下がりにくくなってしまうのです。
また、寝ている間にかいた足の汗で蒸れてしまう、その汗が冷えて汗冷えにつながってしまう、などのデメリットが考えられます。
靴下は、日中、外出するときや、お風呂上がりから寝るまでの間の使用をおすすめします。フローリングが冷たいと感じる場合は、朝起きてから着替えるまでの間に、ルームソックスとして冷え取り靴下を履いてみてはいかがでしょうか。
まとめ

冷え取り靴下は、足冷え対策として作られた、足元の血行を促すのに役立つ靴下のことです。指の形や丈、素材などバリエーションも豊かでさまざまな種類があるため、本記事で紹介したポイントを参考に、自分にあった靴下を選んでみてください。
ケアソク〈あたためる〉は1足編むのにセーター2着分の糸を使用した独自の二重パイル構造を持つ冷え取り靴下です。足をすっぽり包む長い丈で、ふくらはぎの収縮運動をサポートするため、ぜひ試してみてください。
また、ケアソク〈ととのえる〉のインナー5本指構造は、足指を動かしやすいことで血行促進の効果が期待できます。日中の靴下を〈ととのえる〉に代えて、足指を使って歩いてみませんか?
●おうちの冷え取り靴下におすすめ。高い保温力で湯あがりのあたたかさをキープ。
→ケアソク〈あたためる〉シリーズはこちら。
●「インナー5本指」靴下で足指を使った歩行を促す
→ケアソク〈ととのえる〉シリーズはこちら